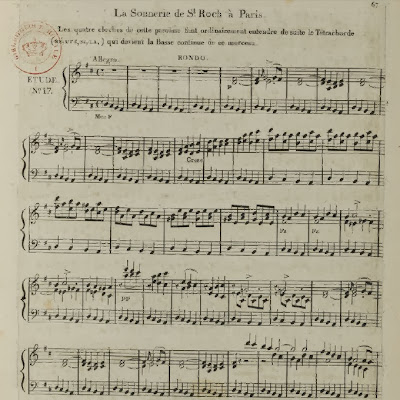夏目漱石 (1867 - 1916) が1907 (明治40) 年に発表した小説『野分』の演奏会の情景には、漱石が実演を聴いた演奏会の曲目が素材として使われている。
演奏会は数千の人を集めて、数千の人はことごとく双手を挙げながらこの二人を歓迎している。同じ数千の人はことごとく五指しを弾いて、われ一人を排斥している。高柳君はこんな所へ来なければよかったと思った。友はそんな事を知りようがない。
「もう時間だ、始まるよ」と活版に刷った曲目を見ながら云う。
「そうか」と高柳君は器械的に眼を活版の上に落した。
一、バイオリン、セロ、ピヤノ合奏とある。高柳君はセロの何物たるを知らぬ。二、ソナタ……ベートーベン作とある。名前だけは心得ている。三、アダジョ……パァージャル作とある。これも知らぬ。四、と読みかけた時拍手の音が急に梁を動かして起った。演奏者はすでに台上に現われている。(中略)
途端に休憩後の演奏は始まる。「四葉の苜蓿花」とか云うものである。曲の続く間は高柳君はうつらうつらと聴いている。ぱちぱちと手が鳴ると熱病の人が夢から醒さめたように我に帰る。この過程を二三度繰り返して、最後の幻覚から喚び醒まされた時は、タンホイゼルのマーチで銅鑼を敲き大喇叭を吹くところであった。
(『野分』第四章より)
1906 (明治39) 年10月28日、東京音楽学校を会場とする明治音楽会の演奏曲目は以下の通りである (『音楽新報』明治39年12月号; 『日本の洋楽百年史』, 第一法規出版, 1966, p.154)。寺田寅彦 (1878 - 1935) の日記によると、漱石は寺田と一緒にこの演奏会に行っている。また、津田左右吉 (1873 - 1961) も日記にこの演奏会の感想を書き残している (中西裕 (2012)「音楽を聴く津田左右吉」『學苑/GAKUEN』865号, pp. 43-55)。
-
バイヲリン、セロ、ピアノ合奏 (マツキー令嬢、ドブラウイチ、サリンガー) 三部合奏曲 ゲーデ作 [Novelletten, Op. 29, or Piano Trio, Op. 42, by Niels Gade]
独唱歌 (ロンゲーカー令嬢) 歌劇バーベット中の舞歌美しき花の咲けるところ ビクトバート作
ピアノ独奏 (マツキー嬢) ロンドン、カプリチオン メンデルソン作 [Rondo capriccioso, Op. 14, by Felix Mendelssohn]
ピアノ、バイヲリン合奏 (ドブラウイチ、マツキー) ソナタ ビートーベン作 [Violin Sonata, by Ludwig van Beethoven]
独唱歌、バイヲリン、セロ、ピアノ伴奏 (ロンゲーカー、マツキー、ドブラウイチ、サリンガー) 四葉の苜蓿花 フアーザードミユツク作
セロ独奏 (サリンガー) アダージヨ パアージアル作
四部合奏曲 (マツキー、ドブラウイチ、多忠基、サリンガー) 甲乙丙 モザルト作 [Piano Quartet, Movements 1-3 by Wolfgang Amadeus Mozart]
レシテーシヨン (ロンゲーカー) 小児と老人に擬す [Recitation]
『野分』の演奏会の5曲のうち最後の「タンホイゼルのマーチ」(March [Einzug der Gäste auf der Wartburg] from Tannhäuser, by Richard Wagner) 以外の4曲は「明治音楽会」の演奏曲目1, 4, 6, 5に対応する。アダージヨの作曲者パアージアルは『野分』の註釈や英訳などで Richard von Perger とされていて、瀧井敬子の著書『夏目漱石とクラシック音楽』(毎日新聞出版, 2018) でもそれに倣っている。
「明治音楽会」の第六番目の曲目「パアージアル作曲」の「アダージヨ」が、『野分』の第三番目の曲目「アダジヨ……パージヤル作」として活版に印刷されているのは、実に面白い。しかし、リヒャルト・ペルゲル (ペルガー) Richard Perger (1854-1911) の作品に、無伴奏チェロ曲「アダージョ」があるかどうかは、不明。 (『夏目漱石とクラシック音楽』, pp.103-104)
ここにあるとおり、チェロの独奏で演奏されるアダージョという曲の存在を確認できないままでは、パアージアルがリヒャルト・ペルガーであるというのは根拠に乏しい。ペルガーの作品からチェロ独奏の作品を探してみると、「チェロとピアノのための4つの小品 Vier Stücke f. Vcello m. Pfte., Op. 5 」と「チェロと弦楽合奏またはピアノのためのセレナーデ 変ロ長調 Serenade (B) f. Vcello m. Streich-Orch./Pfte., Op. 21 」が Hofmeister's Musikalisch-literarischer Monatsbericht に掲載されている。小品集 Op. 5 のほうは、それぞれにカヴァティーヌ、インテルメッツォ、エレジー、フモレスケと固有の題があるのに、それらの題ではなく「アダージヨ」とプログラムに載せるのは不自然に思う。セレナーデ Op. 21 の緩徐楽章なら (そしてそれが Adagio であるなら) ありうるだろうか。
「パアージアル」は「バアージアル」の誤植または誤読とも考えられる。実際に『日本の洋楽百年史』の該当部は「アダジヨーバアージアル作」と書かれている。ヴォルデマール・バルギール Woldemar Bargiel (1828 - 1897) 作曲の「チェロと管弦楽のためのアダージョ Adagio für Violoncello und Orchester, Op. 38 」は、管弦楽またはピアノによる伴奏が必要な曲であるものの、チェロ独奏のアダージョとして広く知られるものであり、一つの可能性として考えられるだろう。
「明治音楽会」の演奏曲目2、ビクトバート (『日本の洋楽百年史』では「ビクトーバート」と表記) 作曲「歌劇バーベット中の舞歌美しき花の咲けるところ」について瀧井は以下のように書き、楽曲も作曲者も不明としている。
第二曲目の歌劇《バーベツト》より舞歌「美しき花の咲けるところ」は不明。作曲者ビクトバートも不明。(「夏目漱石とクラシック音楽」, p.98)これはおそらくヴィクター・ハーバート Victor Herbert (1859 - 1924) 作曲、ハリー・ベイチ・スミス Harry Bache Smith (1860 - 1936) の台本による3幕のロマンティック・コミック・オペラ「バベット Babette 」(1903年初演) より第3幕第22曲 "Where the Fairest Flow'rs are Blooming" で、作曲者「ビクトー・ハーバート」、「ビクトル・ハーバート」と書くべきところを脱字したのであろう。
「明治音楽会」の演奏曲目5、「四葉の苜蓿花(うまごやし)」は四つ葉のクローバーのことであるが、作曲者フアーザードミユツクについては瀧井は同様に不明と書いている (「夏目漱石とクラシック音楽」, p.98)。 Hofmeister's Musikalisch-literarischer Monatsbericht ほかによると、1906年以前に出版された「四つ葉のクローバー」を題とする歌曲としては以下のものなどがあるが、フアーザードミユツクと表記されそうな作曲者は見つからない。ルドルフ・エルネスト・ロイテル Rudolph Ernest Reuter (b. 1888) 作曲の「四つ葉のクローバー」は1907年3月に作曲されている (「夏目漱石とクラシック音楽」, p.104) が、これは『野分』の出版後のことである。
-
Vierblättriger Klee: „Gefunden, gefunden! An’s Herz ich dich drück“ (No. 2) from 6 Lyrische Gedichte, Op. 40 (Köln: Tonger, 1892), by Fritz Lorleberg
Vierblätt’riger Klee: „Gefunden, gefunden! An’s Herz ich dich drück’“, Op. 78 (Bayreuth: Giessel jun., 1897), by Karl Seitz (1844 - 1905)
Four Leaf Clover: „I know a place where the sun is like gold“ (Cincinnati: The John Church Company, 1905), by Charles Willeby (1865 - 1955)
Vierblättriger Klee: „Ein vierblättriges Kleeblatt, das sucht man im Klee“ (Leipzig: Bosworth, 1905), by Carl Bohm (1844 - 1920)
„Vierblättriger Klee, wenn ich dich seh“ aus der Operette „Bruder Straubinger“ (Leipzig: Weinberger, 1905), by Edmund Eysler (1874 - 1949)